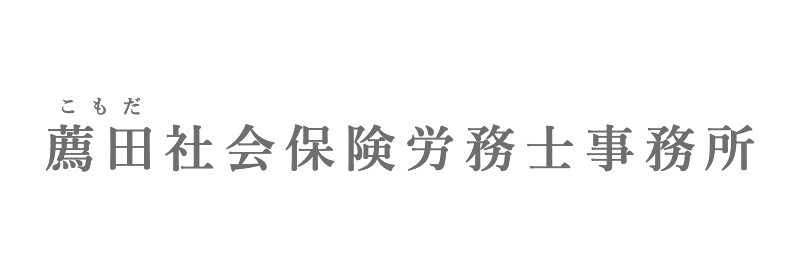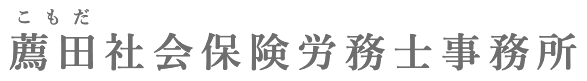Ⅰ.ビジネスと人権推進社労士(BHR推進社労士)について
2025年2月現在、私は全国社会保険労務士会連合会(以下、「連合会」)でビジネスと人権部会の委員を務めている。ビジネスと人権部会は昨今の人権を重視した経営意識の高まりを受け、連合会が設置した専門部会であり、国連ビジネスと人権に関する指導原則に基づく事業運営を行おうとする企業(主に中小企業)の支援を行える社会保険労務士(以下、「社労士」)を養成することを主たる目的としている。
こうして養成されたビジネスと人権推進の支援を行える社労士を、連合会では「ビジネスと人権推進社労士(BHR推進社労士)」と呼んでいる。
ちなみに、社労士がビジネスと人権に取り組む理由は、社労士の事業分野が賃金、労働時間やハラスメント対応などビジネスと人権への対応で必要な項目と近く、日常業務との親和性が高いこと、及び社労士の関与先には中小零細企業が多いことから、わが国においてビジネスと人権に関する指導原則に基づく企業経営を隅々まで浸透させるには、社労士が最適だ、と考えられるためである。
BHR推進社労士を養成するための研修カリキュラムは、ビジネスと人権に関する指導原則の本家本元ともいえる国際労働機関(ILO)駐日事務所の技術支援を受けて組み立てられており、初級編と上級編からなるものとなっている。
ちなみに初級編は、4時間16分かけてe-ラーニングでビジネスと人権に関する基礎的な知識を学ぶ。上級編は実地と対面セッションに分かれており、対面セッションは、グループワーク形式でロープレを含んだ集合研修を2日12時間かけて実施する。なお、対面セッションに参加するためには日本繊維産業連盟の「責任ある企業行動ガイドライン」付属のチェックリスト(*)を用いて実地に受講者が任意に選択した企業でチェックを行い、それについてのレポートを提出するとともに、到達度テストに合格することが要件となっており、この実地のチェックの段階で断念する者も一定程度いることから、本人の意識がある程度高くなければ修了できないカリキュラムといえるだろう。
(*)2024年10月には、厚生労働省国際課とILO駐日事務所がより広い業種をカバーする「労働におけるビジネスと人権チェックブック」を発行している。
なお、上級編の対面セッションは、2023年2月と4月に東京で開催した後、検討準備期間を経て2023年11月から全国6ブロックで満遍なく本格的に開催されており、2025年3月には全国で約600名のBHR推進社労士が養成される見込みとなっている。
私は、BHR推進社労士養成のためのマスタートレーナーの役割を担っており、これまで全国約10か所で上級編対面セッションのファシリテーターを務めてきたが、回を経るごと、すなわち時期が後であるほど受講生のビジネスと人権への関心が高くなり、豊富な専門知識を身に着けた社労士が増加していると実感している。ビジネスと人権に関する報道を目にする機会が増えてきていることも影響していると思われるが、逆に言うと、それだけ企業はビジネスと人権を意識した企業経営を行う必要性が高まっているということだろう。
Ⅱ.中小企業の特性(私見)について
前置きが長くなったが、自身の活動も踏まえて、中小企業にビジネスと人権に取り組んでもらうためにはどういう対応が有効なのか、について考えてみたい。ただし、あくまでも私見であるが・・
まず、中小企業が何らかの取り組み、特にビジネスと人権のように、自社の事業内容からみて直接的に売上増や利益増をもたらすものではないように見える何か、に取組もうとする場合、その動機は何かを考えてみると主に以下のようなものがあげられるだろう。
1.法律改正があり、取り組まざるを得ない状況になった
2.自社に仕事をくれる発注元から、取り組みの要請があった
3.競合他社との差別化のため、自ら率先して取組むことで競争優位を得たいと考えた
1.については、現在のわが国では、ビジネスと人権に関する行動計画(2020-2025)、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料は公表されているものの法制化はされていない。私の事業分野である労働法関係の改正があったときの中小企業の皆様の対応をみていると、義務化されている項目なのか、努力義務にとどまっているかを気にされるところが一定程度存在している印象がある。すなわち、法律で義務化された以上、法律によっては罰則があるためこれに対応しなければならないが、努力義務だとまだ猶予がある、という考え方をするということだ。もっとも、努力義務とされた項目だけでなく、努力義務にすらなっていない項目についても労働者の働きやすさ、働きがいの向上や採用競争力のアップ等を目的に対応するところも多い(3.の動機に該当)ため、中小企業の傾向として一般化することはできないものの中小企業の中にはこういった考え方をするところもある、ということだろう。
なお、特定技能外国人材を受け入れるに際し、繊維業については「国際的な労働基準に適合し事業を行っていること」という要件が追加で課されたが、この国際的な労働基準に適合していることというのは、まさにビジネスと人権への取り組みによって実現されるものであるため、外国人材の受入れという繊維業にとっては死活問題ともいえる分野では、ビジネスと人権への取り組みが法的にも強制されるようになったといえるのではないだろうか。
2.については、法律による強制と同等、もしくはそれ以上に重視しなければならない、という認識を持っている企業も多いように感じることがある。それは自社の売上、利益は自社に対して仕事を発注してくれる企業によってもたらされており、これら発注元企業との良好な関係が自社の存続、発展にとって極めて重要だと認識しているからだろう。
一定の許容範囲はあっても、短納期の要請やコスト削減にもできるだけ応えることで発注元との良好で安定した取引関係を維持しよう、発注元からマイナスの評価を受けないようにできるだけ発注元の要求に応えようと努める中小企業が多いのではないだろうか?
もちろん、ビジネスと人権に取り組んだ企業であれば、自社の無理な短納期発注やコスト削減要求が発注先(サプライヤー)での人権侵害を引き起こす(cause)ことを理解しており、こういった無理な要求はなされているはずである。
現在、サプライチェーン内で大きな責任を持つバイヤー企業は、SAQ(Self-Assessment Questionnaire)を行いサプライヤーにおける人権リスクを把握しようとしている。このとき、この質問事項に回答しようとするサプライヤーの中には、質問事項にありのまま回答すると「×」or「できていない」が多くなることから、そのまま正直に回答することを躊躇するところがあるようだ。バイヤー企業としては、できていない項目に「×」or「できていない」と回答してもらい、サプライチェーン内のリスクをしっかりと把握したいという思惑があるが、正直に回答することで自社に対する評価が下がり、バイヤーとの取引にも悪影響があるのではないか?と危惧するサプライヤーが結構存在する、ということであり、ここに認識のギャップが生まれている。
また、回答を作成するに際しても社長単独、もしくは担当部署のみで行うところが多く、自社のリスクを十分把握しないままの回答となっているケースがあるだろう。人事部門の方のみで回答しようとすると調達部門のことは疎かになるだろうし、逆もまたしかりであるから本来は社内の各部門を巻き込んで自社のリスクを把握してから回答する必要があるのだが、そういった回答は少ないと思われる。特に、労働組合が存在しない中小企業においては、自社内の最大のステークホルダーである労働者の声を聞かないまま回答している、というケースがかなり多いのではないだろうか。
なお、バイヤー側がビジネスと人権についての基本的な考え方、知識を予めサプライヤーに理解してもらい、かつ、アンケートはリスクを把握するためのものであって、これに対する回答で取引関係に影響があるものではない旨をしっかりと伝えるならば、バイヤー側にとって有益なリスク情報が集まりやすくなるのではないだろうか?
3.中小企業でも、ビジネスと人権への対応がますます重要になっていることを理解し、これに積極的に取り組むことで自社の企業価値を向上させ、業績向上に努めているところもあるが、どちらかというとかなり少数派のように思われる。ビジネスと人権への取り組みが、自社の売上増に直接結びつく、というイメージを持ちづらいことも影響しているだろうが、その本質を捉え、長い目で見た場合には自社にとってもプラスの影響があることを理解してもらう必要があるだろう。
Ⅲ.中小企業に対しビジネスと人権を浸透させるには
Ⅱ.1.でみたように、現在、わが国ではビジネスと人権について欧州的な人権DDを義務化するような直接の法制化はなされていない。また、Ⅱ.3.でみたように、中小企業の中には他に先んじて取組みを行っているところも存在しているが、比較的少数派といえる。とするとⅡ.2.のバイヤーによる要請が最も実現可能性が高い方法ではないか?
現在、自社の発注先に対してSAQを実施している企業は多いが、これもいわゆる大企業が中心となっている。この場合でもTier1と呼ばれる自社と直接取引がある発注先への対応にとどまっているところが多く、Tier1の先のTier2、Tier3についてSAQを実施しているところは少数派のようだ。直接の取引がないだけにどこまで踏み込んでいいのか、と躊躇しているという話をお聞きしたこともあり、なるほどその通りだと思う反面、これまでアンケートが送られてきたことがない、という企業こそ人権侵害のリスクが高い可能性があることを考慮するなら、何らかの方法で自社と直接取引がない企業の人権リテラシーを向上させる工夫が必要なのではないかと感じている。
(前述のように発注元から要請があって動く、という企業はそれなりに多い・・・)
そのためには、Tier1企業に働きかけてTier1企業がその発注先に対してSAQ実施するよう依頼したり、Tier1企業だけでなくその発注先の従業員に対する教育に講師を派遣したりするなどの方法を検討する必要があるのではないだろうか?Tier1が単独でTier2への協力ができないなら、人的、金銭的な支援もあり得るのではないか?
ビジネスと人権に関する指導原則14前段では「人権を尊重する企業の責任は、企業の規模、業種、企業活動の状況、所有者、組織構成に関係なく全ての企業に適用される。」とし、規模の大小を問わずに企業には人権を尊重する責任があるとされているが、同時にその後段で「ただし、企業がその責任を果たすためにとる手段の規模や複雑さは、上記の諸要素や企業による人権への悪影響の重大性により異なりうる。」ともされており、サプライチェーンの最上位に君臨する企業は大きな責任を有しているといっても過言ではない。Tier1、Tier2とともにできる限り末端に近いところまで浸透するような工夫をする必要があると思われる。
なお、Tier1、Tier2・・・を支援する際にサポートできる専門家として、前述のBHR推進社労士の活用を検討していただけるとありがたい。